住民税非課税って、年収幾らくらい?
いろいろと、行政上や保険上などで優遇される住民税非課税。
いったい年収幾らぐらいの人のことを言うの???
住民税の場合『均等割(5000円プラス各自治体の決める額)』と『所得割(前年度の課税年収によって決まる・所得の10%)』の2種類で税金が取られる。
収入によっては、「所得割だけ非課税」なんて場合もある。
均等割・所得割とも非課税になる条件
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が自治体の条例で定める金額以下の人
前年の合計所得金額が自治体の条例で定める金額以下の人
自治体によって違うが、某自治体では、住民税上の各基礎控除後や必要経費を差し引いた後の所得が↓の金額より少ない人。
均等割りと所得割が非課税になる条件
《長野市》
- 扶養親族がない…31万5千円+10万円
- 扶養親族がある…31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+18万9千円以下の人
均等割りが非課税になる条件
《横浜市》
- 扶養親族がない…35万円+10万円以下の人
- 扶養親族がある…「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円」以下の人
所得割が非課税になる条件
《横浜市》
- 扶養親族がない…総所得金額等が35万円+10万円以下の人
- 扶養親族がある方…総所得金額等が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円」以下の人
《長野市》
- 扶養家族がいない…35万円+10万円以下の人
- 扶養親族がある方…総所得金額等が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円」以下の人
住民税の対象の計算に含まれないもの
- 障害年金や遺族が受ける恩給や年金
- 雇用保険の失業給付金
- 生活保護のための給付金
- 相続・贈与などによって取得した資産(相続税や贈与税の対象になる)
- 通勤手当のうち10万円まで
なるほど、遠いところに住んで、通勤手当をもらったほうが、住民税上は得になるのね。
住民税は非課税でも、相続税や贈与税はかかってくることもあるわけだ・・・。
ふーん。
ちなみに、老年基礎年金の場合、雑所得の扱いなので、年金額によっては、住民税がかかってくる。
《長野市の場合》
・65歳未満…年金額600,001 円 から1,299,999 円 まででは基礎控除が「600,000円」
なので、配偶者がいない場合、年金額が、101.5万円以下なら住民税が非課税になる。
月の年金額としては、8.4583万円くらい。
・65歳以上…1,100,001 円から3,299,999 円まででは基礎控除が「1,100,000円」
配偶者がいない場合、年金額が、155.1万円以下なら住民税が非課税になる。
月の年金額として、12.925万円。
所得税上の課税所得と住民税上の課税所得は違う
確定申告や年末調整で課税所得がゼロになっても住民税上の課税所得がゼロになるとは限らない。
なぜかというと、同じ名前の控除でも、住民税上の控除と所得税上の控除では控除の額が違うから。
大体は、所得税上の控除の金額のほうが住民税上の控除の金額より大きかったりする。
なので、[所得税上の課税所得>住民税上の課税所得]になる場合が多い。
ちなみに、年収と所得も違います。
課税所得は収入(年収)から、社会保険料や各種の控除を引いたもの。
なので、同じ年収でも、控除の額によって、住民税の所得割の金額が変わってくるということになる。

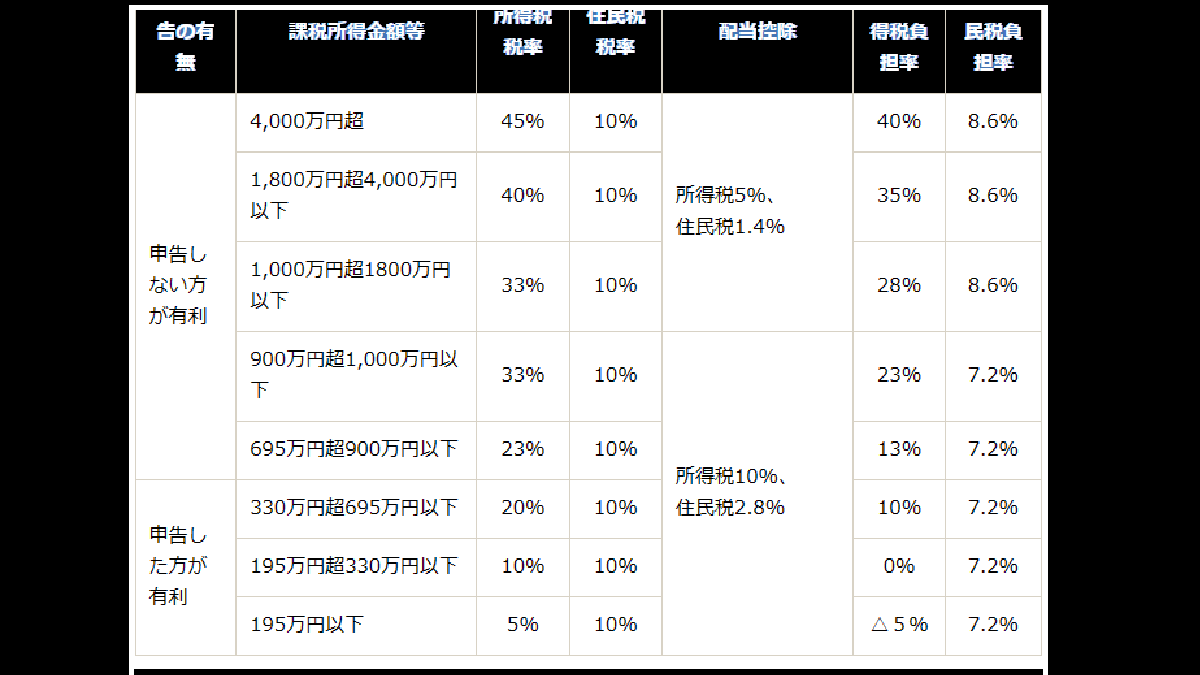
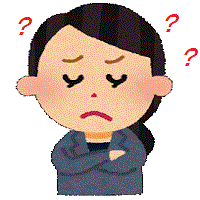
コメント