「〇年〇月〇日に金融機関の預金がいくらあるか?」
これを証明してくれるのが残高証明書。
「通帳があれば銀行残高なんかすぐ判る!」
いや、正確な残高は残高証明でないと実は判らない。
残高証明書が必要なケースや通帳ではだめな理由・残高証明の請求方法をお話しするよ。
残高証明書の使い道
残高証明書は「遺産相続」や「離婚のときの財産分与」などの時使うことが多い。
我が家の場合、父のモラハラが原因で、母と父は別居していた。
母が父と別居した時に、離婚調停を起こしたので、母の預金の正確な残高が必要になった。
しかもモラハラ加害者父との別居した時点での利子を含めた預金残高が必要になった。
母は遠方の施設で療養中。
歩くことに支障があるので、自分で残高を確認に地元まで来ることができない。
さて、どうやって預金の残高を確認すればよい?となり、残高証明書をとった。
ちなみにこの時に使っていた金融機関はJAバンクだ。
通帳では「残高証明書」の代わりにならない
「通帳さえあれば、残高なんてわかるだろう」 と思われる方、それは甘い!
通帳に記載されているのは、記帳した日の残高でしかない。
〇年〇月〇日24時の残高じゃないのだ。
そもそも〇年〇月〇日にピンポイントで記帳するなんて芸当は早々できない。
さらに、遺産分割などの場合は、必要書類として「残高証明書」が必要なのだ。
残高証明申請書
JAバンクの口座のある支店に「〇年〇月〇日時点の預金残高がわかるものが欲しい」と相談にいった。
すると、銀行から
「【残高証明書】というのを申請すれば、日付指定での残高を証明書として出せる」
といわれた。
「残高証明書」の取り方
「残高証明書」の取り方はというと
とのこと。
普通郵便なら、口座の住所に郵送されても、郵便局に転送届を出しておけば、おいらの住所に転送されてくる。
口座別残高の証明書にすることもできるし、すべての口座の残高を証明することも可能だそうだ。
「残高証明申請書」を自筆で書くことができない場合は?
当時、母は自分で「残高証明申請書」を書くことができたので、施設に「残高証明申請書」を郵送した。
書き終えたら、同封した返信用封筒に入れて、返送してもらう予定とした。
でも、もし母が認知症になったり、目が悪くなったりして自力で「残高証明申請書」を書くことができない状態になったらどうするんだろう?
成年後見人なら代理申請が可能
家庭裁判所で選任された成年後見人なら、JAのいろいろな手続きが代理でできるそうだ。
ただし、成年後見人制度は、認知症とかで判断能力が低下した人のための制度。
身体的に署名ができない場合、例えば、目が見えなくなったり、手が動かなくなったりしたら、どうしたらいいんだろう?
医師の診断書持参なら代理申請が可能
「本人が申請書を書くことができない。」
という医師の診断書があれば、代理人の申請でも認めてくれるらしい。
相続のための残高証明書の発行方法は?
相続のための残高証明書が欲しい場合、もう亡くなっている人の預金残高の証明書が必要になるわけだから、まさか、申請書を死んだ人に書いてもらうわけにもいかない。
そんな場合は、
以上を持って、取引店へ行って残高証明書を発行してもらう。
残高証明書の値段は?
残高証明書の値段は1通500円。
金融機関によっては値段が違うかもしれない。
ちなみに上の話は、おいらの住んでいる地域のJAバンクの手続きとお値段。
ほかの地域のJAバンクでは、ちょっと手続きの方法が違ったり、金額が違う可能性はある。
また、JAバンク以外の銀行の場合、これまた手続きが違う可能性がある。
例えば、三井住友銀行は880円、ゆうちょ銀行1,100円円、みずほ銀行880円、三菱UFJ銀行770円といった具合。
今は手数料がまた違っているかもしれない。
窓口とインターネットでの手続きでは値段も違ってくるし、窓口でしか申請を受け付けないという金融機関もあるようだ。
銀行だけではなく、証券会社などの金融機関も残高証明書を発行してくれる。
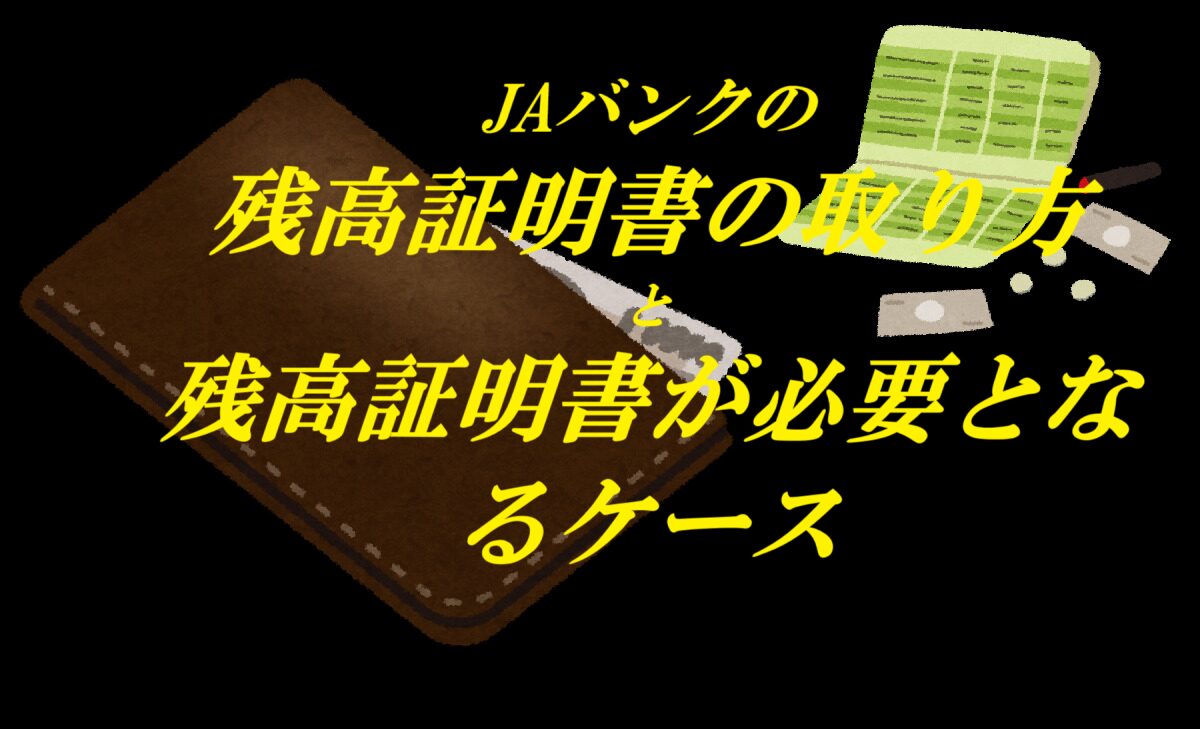
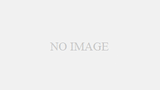

コメント
>相続のための残高証明書の発行方法は?
>実印および印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)または依頼者がJAバンクに預金を持って>いた場合には依頼者の貯金取引印
申請者の実印と印鑑証明書のことですか?
依頼者とは申請者のことですか?
申請者の実印と印鑑証明書のことです。
依頼者とは申請者のことです。