なんだかわかりにくいと感じてしまう住民税というもの。
いったいなんでわかりにくいんだろう。
このブログでも何度か住民税については取り上げているんだけど、やっぱりわかりにくいと感じてしまう。
住民税についてもうちょっと掘り下げてみたい。
住民税の目的
住民税は、地域社会の行政費用をできるだけ多くの住民に分担してもらうという目的で徴収される税金のひとつ。
個人に課す個人住民税と、法人に課す法人住民税がある。
住民税には2つの納税先がある?
住民税には、市町村民税(23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)がある。
市町村民税は市町村へ、と県民税は都道府県へと納税されるわけなんだけど、これを住民税として徴収しているわけだ。
住民税には2つの課税方法がある
住民税には納税先とは別に、「所得割」「均等割」という2つの課税方法がある。
住民税均等割
住民税均等割りは「所得金額にかかわらず定額で課税される」住民税。
住民税均等割の標準税額
これに平成26年度から令和5年度までの間、地方自治体の防災対策に充てるため、均等割額は都民税・区市町村民税それぞれ500円が加算されている。
なので
ここまでは、全国一律。
さらに、住んでいるところによって+αの税金を徴収されることがある。
住民税所得割
住民税所得割は前年の所得金額に応じて課税される。
住民税所得割の税額
住民税の所得割は、市町村民税6%+道府県民税4%=合計10%。
年収から、各種控除を引いたあとの所得から10%(1割)の住民税が徴収されるということだ。
所得税の控除と住民税の控除は同じ名前でも控除額が違う
所得税上の控除と住民税上の控除は同じ控除名でも控除額が違う。
たいていの場合、住民税の控除額のほうが少ないため、所得税の所得より住民税の所得のほうが大きくなる。
要は、所得税が非課税でも、住民税の所得割は非課税にならないという事態が生じる。
住民税が非課税になるのはどんな人?
住民税が他税になる基準は、市自治体によって微妙に違う場合がある。
東京都の場合は「均等割・所得割の両方が非課税になる」ケースと「所得割のみ非課税になる」ケースがある。
住民税の「均等割・所得割の両方が非課税になる」のはどんな人?
東京・東京23区内の場合、住民税の均等割りが非課税となるのは
⇒35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
⇒45万円以下
これはあくまで東京都の例。
他の自治体を見てみると
⇒ 令和2年度以前 :31万5千円
⇒令和3年度以降: 41万5千円
⇒令和2年以前: 31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+18万9千円 令和3年以降:31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+28万9千円
というように実際に住民税が非課税になるかどうかは自治体によって基準が違ってくる。
住民税の所得割が非課税になる人
東京23区で所得割が非課税になるのは、前年中の総所得金額等が、下記の金額以下の人。
⇒35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下
⇒45万円以下
某自治体では
⇒令和2年度以前35万円
⇒令和3年度以降45万円
⇒令和2年度以前:35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円
⇒令和3年度以降:35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円
というように住民税の所得割が非課税になる基準も自治体によって変わってくる。
住民税の課税期間
所得税はその年の1月1日から12月31日までの所得に課税される。
が、住民税の場合、前年度分の所得が課税対象となる。
住民税は1月1日の住所地で課税される
住民税は前年度分の所得に対して、1月1日現在の住民票上の住所地で徴収される。
ここもわかりにくい点。
例を挙げれば、平成26年1月1日に転居し、住民票上の住所を移した場合、平成25年1月1日から平成25年12月31日までの所得が平成26年1月1日の住民票上の住所地で課税される。
住民税を納める方法は2つある
住民税の納税方法にも2種類ある。
サラリーマンの住民税の徴収方法は特別徴収
サラリーマンの場合、住民税は特別徴収という形で住民税を納める。
特別徴収は住民税を6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、会社が取りまとめて住民税を納付するもの。
ただし、年の途中で転職した場合などは、基本的には普通徴収になる。
サラリーマン以外の人は普通徴収
給与から税金を天引きできない人は、普通徴収という方法で住民税を納める。
毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付され、この納付書により市区町村役場や金融機関などの窓口で支払いう。
住民税の納期は6月・8月・10月・1月などの年4期。
支払い月は各市区町村によって違う場合もある。
給料+給与所得以外の収入がある人の住民税の納め方
サラリーマンでも給料以外の収入がある人は、2通りの方法を選ぶことができる。
たとえば、株や不動産などの売買の利益、副業の収入などで収入があった場合などにも住民税がかかってくる。
すべて特別徴収
特に手続きしていないと、給与所得以外の収入分の住民税もすべて特別徴収として会社からもらう給料から天引きされる。
給与部分は特別徴収、他は普通徴収
給与にかかわる住民税部分を会社で天引き。
その他の収入は普通徴収として市町村に直接住民税を納めることができる。
ただし、副業であっても、副業での収入が給与である場合、すべて特別徴収となる。
この場合、メインとなるひとつの会社の給料から住民税を天引きされる。

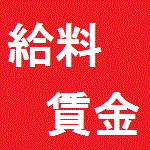
コメント