母の死亡保険金の請求に行った。
ものすごく簡単に保険金の請求手続きが済んでしまった。
正確に言うと、母が入っていたのは、JA共済なのだけど。
ある程度大きなお金を一時的に払って、満期または契約者が死亡した時に給付金が払われるというもの。
死亡給付金請求は手続き簡単
JA共済の死亡給付金(死亡共済金)の請求手続きは、拍子抜けするほど簡単に済んだ。
死亡給付金(死亡共済金)請求手続き必要書類
死亡給付金(死亡共済金)の請求に必要な書類などは以下のもの
記載する書類は2枚
請求時に記載する書類は2枚。
1枚目は「亡くなった人の情報を記載する書類」
を記載する。
2枚目は請求者(受取人)の情報
を記載する。
請求から受け取りまでは1から2週間かかる
死亡給付金(死亡共済金)の請求から、受取(受取人の預金通帳への入金)は、特に書類に不備がなければ、大体1から2週間程度。
受取人と請求者が違う場合
今回の死亡給付金(死亡共済金)の受け取りがすごく簡単に済んだのは、死亡給付金(死亡共済金)の請求者がもともと受取人として指定されていたためだ。
これが、受取人と請求者が違う人の場合、もっと必要な書類が増えて、かつ、書くものも増える。
特に、事前に指定代理請求特約を付けていなかった場合、「受取人の委任状」やらも必要になる。
この、委任状は原則的に「直筆」でなければならない。
受取人が自分で字を書ける状態にないと、ものすごく、面倒なことになる。
指定代理請求特約
指定代理請求特約は
というもの。
この、指定代理請求特約はJAの共済にもともとついている特約。
今、一般の生命保険でも、この指定代理請求特約がついているものが多い。
ほかのJA共済でもともとついている特約としては、「生前給付特約」というものがある。
JA共済「生前給付特約」
「生前給付特約」は
というもの。
JA共済は保険のようなもの
JAは要するに農協のこと。
いろいろな事業を行っていて、共済事業は一般の保険とよく似ている。
と内容も幅広い。
農業従事者でなくても加入できる
JAは農協のことだが、必ずしも、農業従事者でなくても利用できる。
JAバンクが窓口になっていて、共済だけでなく、各種ローン、銀行業務なども行っていてる。
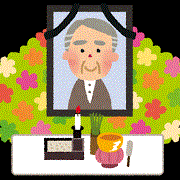


コメント